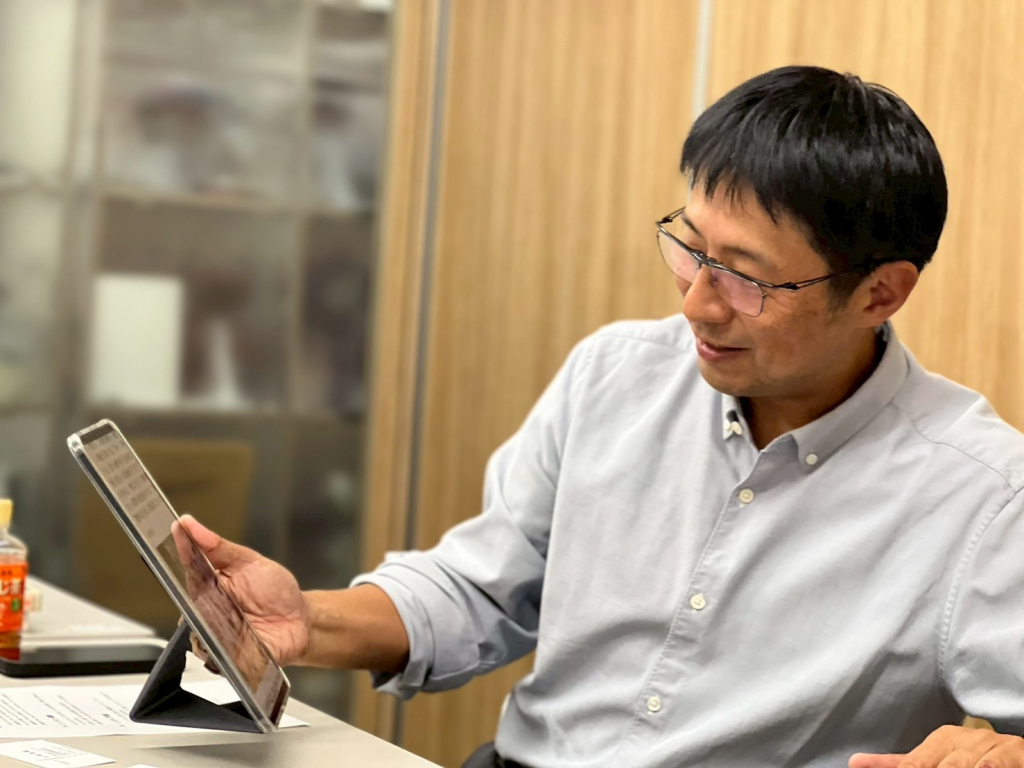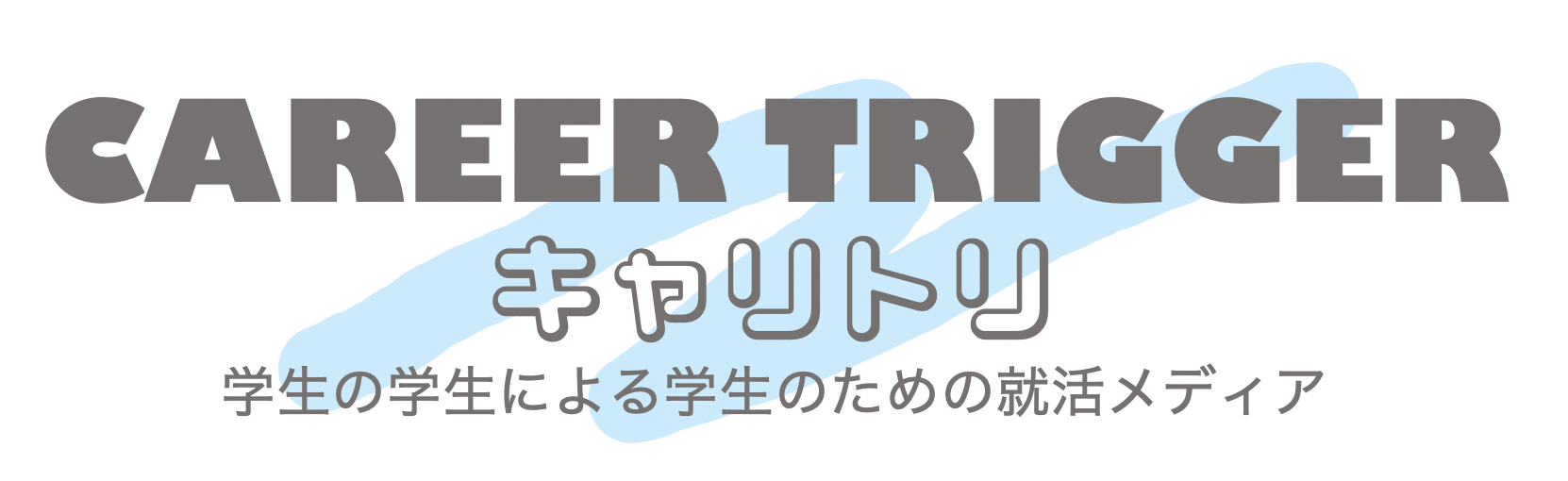カウンターウェイトに込めた夢~音頭金属株式会社が描く製造業の未来図~
皆さん、こんにちは!キャリトリ編集部です。
今回は、製造業の枠を超えてグローバルに挑戦し続ける音頭金属株式会社の音頭則靖社長にお話を伺いました。ニッチな業界でありながら、その情熱的な経営哲学と国際的な視野には、就活生の皆さんにとって多くのヒントが隠されています。
ニッチだからこそ価値がある
音頭金属の主力製品は、建設機械に欠かせないカウンターウェイトです。ショベルカーなどの重機の後ろについている重りのことで、機械が作業中に転倒しないよう重要なバランスを保つ役割を担っています。
「誰も知らない部品だけど、これがなければショベルカーは動かない。まさに縁の下の力持ちなんです」と語る音頭社長。製品には2つの製造方法があり、鋳物は型を使って複雑な形状を作れるが高価、一方製缶品は鉄板を溶接した箱にスクラップを詰め込む方式でコストを抑えられます。街中の工事現場では鋳物製、24時間稼働する鉱山では最大80トンもの製缶品が使われているそうです。
普段見えない部分で社会インフラを支える仕事への誇りが、音頭社長の言葉の端々から感じられました。
年間100億円規模、そして驚くことに、国内で同じ仕事をしている会社はほんの数社しかありません。まさに「知る人ぞ知る」特別な分野のものづくりなのです。

危機を転機に変える ―海外展開への熱い想い―
音頭金属の大きな転換点は、東日本大震災でした。電気代の高騰により、従来の日本での鋳物製造が困難になったのです。「電気で鉄を溶かすと高くてしょうがない」という状況に直面した音頭社長は、「自分が楽しく、かつ会社が存続できる方法を見つけよう」と前向きに考えました。
その結果生まれたのが、中国、ベトナム、インドネシアとの積極的な連携です。現在では売上の7割が海外調達による商社的機能を併せ持つ、ユニークな製造業として発展を遂げています。「日本だけで作っていてもしょうがない」という発想から、中国では商社を設立し、インドネシアには工場を建設。ベトナムにも営業所を構えるなど、逆境をチャンスに変えた経営判断でした。
音頭金属の売上は、社長の入社した2000年当時から比べると、今ではおよそ約2倍の規模に成長しています。
「実は、作っている量はそれほど変わっていないんです。鉄の価格が20年前の約2倍になったことで、売上の数字も大きく見えるだけなんですよ」と、冷静に分析されているのも印象的でした。
世界で戦う人材を育てる ―17年間の国際採用戦略―

音頭社長の最も印象深い取り組みは、海外人材の積極採用です。17年前から中国の一流大学出身者を中心に毎年2人ずつ採用し、現在では技術部門のトップや海外拠点の責任者の多くが外国人という、中小企業としては驚異的な体制を構築しています。
「優秀な人材は本国のトップクラスの大学に集まっている。だからこそ日本に来る前に現地へ出向き、直接採用活動を行うのです」という考えのもと、現地まで足を運んで採用活動を行います。面接では「今すぐサインできるか」と覚悟を問う真剣勝負の姿勢で臨み、本当にやる気のある人材を見極めているのです。
中国の北京航空航天や北京科技大学、インドネシアのガジャマダ工科大学をはじめとする有名理系大学から採用した人材の多くが、今では重要なポジションに就いています。「離職率で見ると外国人の方が残ってくれる。少なくとも半分は残ってくれる」という実績も、この戦略の成功を物語っています。
最後に日本人大学生を採用したのは9年前で、立教大学出身の方。現在はインドネシアで現地の方と結婚し、30代で現地法人の役員として活躍されているそうです。
社員の夢を支える経営哲学 ―「やりたい」を実現する環境づくり―
「最初は自分が楽しければいいと思っていました。会社の駐車場でプロレス興行を開いたり、フットサルコートを作ったり、好き勝手やっていました」と笑いながら振り返る音頭社長。しかし海外人材が入社してから大きく変わったといいます。
「外国人社員が『これやりたい』『あの国でビジネスしたい』と言い始めて、それを聞いているうちに、社員がやりたいことを実現できる環境を作ることが私の役割だと気づきました」
実際に中国人社員から「インドでビジネスを始めたい」という提案があり、そのために日本国籍を取得して帰化までした社員もいるそうです。「彼には、会社の将来を任せられる力を感じる」と語る音頭社長の表情からは、深い信頼と愛情が感じられました。
現在では海外法人役員、マネージャー、グループ長のうち5人ほどが外国人で、技術部門のコアメンバーは「みんな外国人」という部署もあるとのこと。社員の「やりたい」を後押しすることが、会社全体の成長につながっているのです。
最先端技術への挑戦 ―AIが拓く製造業の未来―
音頭金属は現在、中国のパートナーと共にAI技術を活用した製造業の革新にも挑戦しています。「中国では中小企業でもAIロボットをどんどん導入している。日本でもそれを販売したい」という発想で、自社工場を実験場として新技術の導入を進めています。
「中国の合弁パートナーはブラックライト企業を目指している。電気を消してもAIで工場が動き続ける会社です」と、まるでSF映画のような未来像を語る音頭社長。日本では製造現場でのAI活用がまだ限定的な中、この取り組みは非常に先進的です。
プログラマーの採用についても「AIの発達で中途半端な能力の人は淘汰される。Microsoftでもプログラマーの採用を減らしている。だからこそ、本当に優秀なAI人材が中小企業にも来てくれるチャンスだ」と前向きに捉えています。今後はインド人のAI技術者の採用も予定しているそうです。
求める人材像
音頭社長が最も重視するのは行動力です。「やりたいことが明確でなくても、『はい』と言える人、考えすぎずに行動できる人がいい」と語ります。
面接では就活のための活動より、「学生時代にいろんなことをやっていた方が、就職してから活かされる」という考えから、純粋に好きなことに打ち込んだ経験を重視しています。
地頭の良さについても独特の見解を持っています。「理解力が早いのは確かに仕事がやりやすい。でも地頭があまり良くない人が、地頭の良い人に釣られて余計なことをし始めるのが一番困る」と苦笑い。「軽自動車なのにスーパーカーと同じことをしようとしても無理」という例えで、自分の能力に合った役割で着実に成果を出すことの重要性を強調されていました。

グローバルなネットワーク ―多様性あふれる職場―
音頭金属の国際色の豊かさは、社内の飲み会の写真からも伺えます。「部署ごとに飲み会を開くと、日本人がほとんど写っていない」という状況で、ベトナム人、アメリカ人、中国人、インドネシア人、さらにはミャンマー人まで在籍しています。
特に印象的だったのは、面接の1週間後にクーデターが起こったミャンマー人の話。現在は親から「軍隊に徴兵されるから絶対帰国するな」と言われているそうで、グローバル情勢の複雑さを感じさせるエピソードでした。
学生へのメッセージ ~好奇心と行動力で未来を切り開こう~

音頭社長から就活生への最大のメッセージです。
「学生時代はいろんなことをやった方がいい。就活のためではなく、純粋に好きなことに打ち込んでほしい。わざわざ就職活動のために何かをしても意味がない」
音頭金属のような企業では、世界を舞台に活躍したい学生にとって理想的な環境が待っています。ニッチな業界だからこそ、一人ひとりの影響力が大きく、年齢、国籍に関係なく早い段階から重要な仕事を任せてもらえる可能性が高いのです。
音頭社長の言葉からは、未知への挑戦を楽しむ精神がひしひしと伝わってきます。
「やる気があれば何でもやらせてもらえる」という環境で、グローバルな視野を持ちながら自分の可能性を試してみませんか。音頭金属のような企業との出会いが、皆さんの人生を大きく変えるきっかけになるかもしれません。音頭社長から就活生への最大のメッセージです。
取材を終えて
音頭社長との取材を終えて感じたのは、製造業に対する従来のイメージが大きく変わる瞬間でした。多くの人が「きつい・汚い・危険」といったネガティブな印象を持ちがちな業界ですが、音頭金属では「国際的で革新的、そして挑戦に満ちた職場」という全く異なる未来を描いています。
特に印象的だったのは、音頭社長自身が社員の「やりたい」を大切にし、外国人社員も積極的に受け入れていることです。この姿勢は、単に企業の存続戦略としてだけでなく、真の意味での多様性尊重と成長の文化を築いていると感じました。
また、AIやロボット技術の導入による製造現場の変革にも積極的な姿勢が、これからの製造業の将来像を示しています。大企業とは違い素早く柔軟に動ける中小企業の強みを活かし、「新しいことに挑戦できる自由な環境がある」という点は、成長したい若い人材にとって大いに魅力的に映るはずです。
私は、日本の製造業の未来を支えるのはこのような「柔軟で挑戦的な中小企業」であり、音頭金属のような会社が広く知られることが重要だと思います。就活生に対しては、「枠にとらわれない働き方やグローバルな挑戦を望むなら、こうした企業こそが大きな可能性を秘めている」という視点を伝えたいです。
音頭社長の熱い思いや実際の現場の話を聞くことで、就活生の皆さんにも自分の未来に対する視野が広がり、新しいキャリアの選択肢として製造業に興味を持ってもらえたら嬉しいです。
音頭さん、本日は貴重なお時間ありがとうございました。皆さんの就活や将来について考えるきっかけとなるような、素敵な企業や人物を引き続きご紹介していきます。次回もお楽しみに!